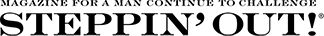CULTURE





スタイリング / 西村哲也
ヘア&メイクアップ / 砂原由弥(UMiTOS)、シラトリユウキ(UMiTOS)
文 / 岡田麻美
1941年、日本が真珠湾攻撃をする7日前の上海が、映画『サタデー・フィクション』の舞台。
当時の上海は日中欧の諜報部員が暗躍し、機密情報が行き交うスパイ合戦が繰り広げられていた。スパイには軍人もホテル支配人も、女優もいる。『蘭心大劇場』で公演される新作演劇のため、上海に人気女優のユー・ジン(コン・リー)が現れた。彼女は舞台稽古に参加しながら諜報活動をはじめ、日本軍人から暗号を聞き出す任務を受ける。資料として渡された写真には、日本海軍少佐の古谷三郎(オダギリ ジョー)と若い頃のユー・ジンに似た妻が写っていた。その妻は、以前スパイ活動中に殺害した女性だった。
本作を監督したロウ・イエは、中国の検閲と戦いながら『天安門、恋人たち』など作りたい作品を貫いてきた人だ。監督の両親は今回の撮影場所でもある『蘭心大劇場』でかつて裏方として実際に働いており、幼少期の監督は劇場と楽屋、虚と実を行ったり来たりする世界を覗き見てきた。その時の奇妙な感覚を、戦争前夜のスパイを扱った原案小説を読んだ際に味わったという。
オダギリはそんなロウ・イエ監督から「最初から決めていたのはオダギリさんで、彼がこの作品を左右すると言っても過言ではないです」と評されている。演じた古谷は、悲しみを背負いながら任務のため上海にやってくる。オダギリは突然妻を失った遺恨だけではなく、男の弱さや危うさ、様々な側面を役柄に宿させているように見えたが、すべては現場で、大先輩でもあるコン・リーとのセッションの中で育まれたと話していた。成り立ちも完成も、奇跡のような作品について話を聞いた。
モノクロに対する感覚として、まずあるのは潔さなんですよ
台本を読まれてどのような印象を持ったのかお聞きしたいと思っていたんですが、先ほどスタッフの方から、制作の途中段階からオダギリさんが参加されていたと伺いまして。まず本作にはどういう経緯で出演を決めたのかお聞きしたいです。
オダギリ 経緯としては、〈アップリンク〉の浅井 隆さんからご連絡をいただいて、「ロウ・イエ監督と映画を作るので、出演してくれないか?」とお誘いいただいたのが最初でした。コロナ禍になる全然前、6年以上は前だったんじゃないかと思います。それから少し経って、監督とオンラインで顔合わせをしたんですよね。そこで、最初に読ませていただいた決定稿前の台本に関して、いくつか僕も気になるところがあったのでお話して。お互い前向きに直していきましょう、みたいな話になったんです。太平洋戦争直前の時代設定ではあるけど、監督自身、戦争における正義や悪を描こうとしているわけではない。ただ、戦争に関しては各国どうしても歴史認識の違いがありますし、そうした作品に関わる事で政治的なイメージを負わされることもあるので、海外の作品に参加する時は特に気にしなきゃいけないことは多いんですよ。ロウ・イエ監督は、それもひっくるめて打ち合わせを重ねていきたい、一緒に作っていきたいと言ってくれる監督でした。
台本は現場でも日々変化があったと伺っているのですが、撮影場所の上海へ渡る前に日本で読んでいた台本には、どういう印象を持ちましたか。
オダギリ いや、複雑な台本だなと思いました。いくつもの要素が入り組んで進みますからね。戦争前夜の上海で、戦争に関わる人たちもいれば、舞台制作に向かう人たちもいるじゃないですか。物語の中には、スパイ合戦や恋愛、催眠術や騙し合いみたいなこともあって。決してシンプルな映画であるとは思わなかったですね。上海に入るまでは、僕もちゃんと理解できていなかったような気がします(笑)。
ロウ・イエ監督について、オダギリさんは「本当に映画が好きな、小学生みたいな方。純粋で色んなことに挑戦したくて、映画への愛が滲み出ている」とコメントされています。監督の作品を拝見すると、厳しい目線を投げかける側面もあると思うのですが、オダギリさんはどんな風にもの作りをする方だと感じましたか?
オダギリ 役者にもスタッフに対しても、コラボレーション的なもの作りを求め、楽しんでいらっしゃるように感じました。役者と、台本や役柄のことを話すのも好きそうだし、役者だけじゃなくいろんなスタッフの意見を聞き取りながら、自分の映画に吸収して固めていく人だという印象があります。とにかく現場が好きなんだろうなと思うし、即興的な芝居やハプニングをすごく喜ぶんですね。子供みたいな笑顔になったりして、ほんとに純粋に楽しんでいるように見えました。
監督が喜んだハプニングというのは、具体的にはどういうシーンでしたか?
オダギリ 予測のできない何かが起きた時に生まれる、人間味や面白さが好きなんだと思うんです。例えばテーブルの上でグラスがこぼれそうになったりすると、役者は気になってしまうものだし、日本だったらというかほとんどの監督がNGにすると思います。でもロウ・イエ監督の現場ではとりあえず止めずに続けるんです。監督特有のスタイルなんですが、とにかく長回しで、平気で3〜4シーンを一気に撮ってしまう。だからグラスがこぼれようと、人が転ぼうと、何があってもとにかく最後までやろうっていう意識なんですよね。僕らは一瞬「あっ」って思っちゃうけど、それをうまく芝居に取り込んでいくしかないし、そういう意味でも即興性を含んだクリエイティヴな現場だとは思いますね。
アクションのシーンなどは特にカット割りが多く感じたのですが、撮影自体は長回しのシーンが多かったのですね。
オダギリ 見ている限り、絵コンテやカット割りをしっかり作り込んで進めている現場ではなかったです。カメラを5、6台用意して10分ぐらい回す、それを10回近く繰り返すっていう……そういう毎日でした。いやまあ正直なところ、繰り返すこと自体には単純に飽きちゃうんですけど、さっきお話したように即興的なものを監督は好むので、こっちも同じ芝居をしないように心掛けるじゃないですか。なので、本当の意味で飽きることはないんですけど、「もういいんじゃない?」と言いたくなるくらい繰り返していました(笑)。
オダギリさんが演じた古谷は、妻を殺害された日本海軍少佐で、役のキャリアやバックボーンは映画では詳しく描かれていませんが、古谷をどういう人物だと考えて演じましたか?
オダギリ 俳優がそういう話をするのは気恥ずかしいので、少し話題を変えると、最初にも話しましたが、監督とは色々な打ち合わせを重ねたんですね。特に僕が気にしていたのが、海外の作品で日本を扱う時によく見られる勘違いや、ステレオ・タイプなイメージを1つでも少なくしたかったんです。例えば、コン・リーさん演じる役との関わり方についてでした。海外の人にとっては普通でも、日本人は彼女に対してそんなことはしないだろう、そんな言葉を選ばない、そういう行動をとらない、など。同じアジアの国でも、距離の取り方や、関係性の深め方はまったく違うと思うんです。しかも1941年に生きていた日本人ですからね。古谷を作り直す作業は時間がかかりました。監督の要請で、いくつかは僕が書き直したシーンもありました。
そうだったのですね。共演者のコン・リーさんは数々の名作にご出演されてきた大女優で、オダギリさんも作品をご覧になってきた方だと思いますが、現場でどういう風にコミュニケーションを取っていましたか?
オダギリ いやもう、驚くくらい穏やかで優しいんですよ。コン・リーさんの方から、「あなたの作品、何本か観ています」と話しかけてくださったり。あんな大女優からそんなことを言ってもらえるなんて、絶対に嫌いにはなれないですよね(笑)。それにフランクで全然壁を作るような方じゃなかったので、周りから変に気を遣われている感じもせず、逆にみんなに対してリスペクトを持っているのがわかりました。その人柄が、同じ中国系の俳優やスタッフからも愛され、信頼が厚い理由なんだろうなと感じていました。
オダギリさんご自身も映像の編集をされますが、出来上がった作品をご覧になって驚いたシーンなどはありますか?
オダギリ 僕の記憶では、撮影中はまだ監督もカラーにしようかモノクロにしようかと悩んでいたんです。「絶対に全編モノクロでいった方がカッコ良いですよ」みたいなことを伝えていたんですけど、出来上がりを観た時にモノクロのカッコ良さが際立っていたので、意思を貫いた監督に尊敬の念を持ちました。モノクロっていうだけで、制作陣の中には興行的な心配から、拒否反応を示す人もいるんですよね。よくそれを説得されたなと。あと、あれだけアクションやカット数も多い作品なのに、説明的な音楽を付けていない。そういうところも含めて洗練された作品だと感じましたね。『ヴェネチア国際映画祭』に出品された時に現地で初めて観たんですけど、純粋にカッコ良い映画だなと感動しました。
オダギリさんの中で、モノクロの映像の良さとはどういうところにありますか? 映画の原点はモノクロの映像なのでそこへの憧れがあるとか、また、この作品は現実と演劇の狭間を行き来するシーンもあって、夢うつつのような領域が個人的にはモノクロであることで馴染んでいるように感じました。
オダギリ 僕の中でモノクロに対する感覚として、まずあるのは潔さなんですよ。色に頼らない姿勢、まずそこにカッコ良さを感じますね。カラーの映画だと、色を意識せざるを得ないので、画面の構成として、どうしても色を置いていきたくなるんです。本来なかったものをどんどん付け足してしまいがちで、例えばそれを小手先と言うのであれば、そういうことをまったく頭から外せるモノクロっていう選択は憧れます。それに白と黒だけと言いながらも、色の違いを感じさせるグラデーションがちゃんとあるじゃないですか。そういう美しさ、面白さもあると思っているので、僕も作品を作る立場として、一度は全編モノクロの作品を作りたいなっていう想いはありますね。
先ほど少しお話いただいた音楽についても。舞台のシーンでは楽団の演奏があるからか、いわゆる劇伴がないことにびっくりしました。オダギリさんは映画に音楽を入れないことで、どういう効果があると思っていますか?
オダギリ 映画にとって、音楽ってすごく説明的なものだと思うんです。感覚的に、ここは哀愁があるとか楽しいとか、こういうムードで観てくださいって誘導しやすいじゃないですか。緊迫感なんて、音楽が一番作り出しやすい要素ですよね。逆に言うと、音楽で説明しないということで、観ている側のイマジネーションは膨らむと思うし、誰かの概念に引っ張られず自由に観ることができると思います。でもだからこそ、観客を信用しないとできないんです。そこまでちゃんと観てほしいし楽しんでほしいっていう、監督の気持ちの表れだという気がしますね。
撮影場所の上海には、2ヶ月もの長期間滞在されたそうですね。撮影以外の時間は、上海の街を楽しみましたか?
オダギリ そうですね。撮影はコロナ前でしたし、撮影のない日も多かったので、街をブラついたりもしました。ちょうどこの撮影時、自分が監督した映画『ある船頭の話』の準備中でもあったんですよ。現地の人から「上海から車で2時間ぐらい行った古い街に、船頭の人がまだいる」っていう話を聞いて、そこに見学に行ったりもしました。結構アクティヴに、ご飯を食べに行くような気軽な感覚で、色々な場所を見に行きましたね。だから、コロナ禍で上海の人々が大変な思いをされていた時期は、自分がお世話になった地域だったこともあり、胸が痛かったです。無事に公開を迎えて、みなさんに観てもらえたら嬉しいですね。

©YINGFILMS
『サタデー・フィクション』
監督/ロウ・イエ
出演/コン・リー、マーク・チャオ、パスカル・グレゴリー、トム・ヴラシア、中島 歩/オダギリ ジョー、他
11月3日全国公開
【WEB SITE】
www.uplink.co.jp/saturdayfiction
【X】
@SatFictionJP
INFORMATION OF JOE ODAGIRI
出演する石井裕也監督作の映画『月』が公開中。配信ドラマ『僕の手を売ります』が〈FOD〉・〈Amazon Prime Video〉にて配信中。
映画監督としても活動し、長編映画監督デビュー作『ある船頭の話』(2019)は『ヴェネチア国際映画祭』にも出品され、世界の注目を集めた。
【WEB SITE】
dongyu.co.jp/profile/joeodagiri