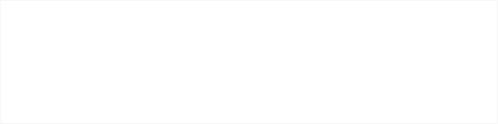CULTURE



藤原季節の幻の初主演映画『東京ランドマーク』が公開。大切な仲間と紡いだ青春の物語を毎熊克哉と語る
MAY. 18 2024, 11:00AM
スタイリング / (藤原)入山浩章
文 / 多田メラニー
俳優の藤原季節がデビュー10周年を迎えた昨年、『デビュー10周年記念 藤原季節特集』と銘打った特集上映が〈テアトル新宿〉で2週間限定のレイト・ショーとして開催された。劇場公開初となる配信舞台『たかが世界の終わり』をはじめ、ラインアップしたのは彼のキャリアを語る上では欠かせない映画の数々。この時、制作から約6年の歳月をかけて初めて封切られたのが、撮影当時25歳の藤原による映画初主演作『東京ランドマーク』だった(大きな話題を呼び、後に『TAMA映画祭』、〈シネ・リーブル梅田〉、〈アップリンク京都〉でも上映)。映画を手掛けたのは、映像制作集団「Engawa Films Project」(通称・エンガワ)。本作で脚本・監督・撮影・編集を担当した林 知亜季(ともあき)、俳優の柾 賢志、毎熊克哉、佐藤考哲から成り立ち、藤原、そして共演の義山真司とは10年以上の付き合いとなる。
物語は、コンビニのバイトで生計を立てる楠 稔(藤原)と親友のタケ(義山)、そして家出中の女子高生・桜子(鈴木セイナ)が出会うところから始まる。家族や友人、生きる上では切り離せない人と人の繋がり。先行きの見えない不安な日々にもがくこともあれば、変わらない存在に救われることもある 彼らの生活を通して心に広がっていくのは、身に覚えのある感覚ばかりだ。長く伸びた前髪から覗く稔の瞳は、観賞後しばらく経った今も忘れることができない。
『東京ランドマーク』は、5月18日より〈新宿K’s cinema〉から全国公開へと向けてさらに羽ばたいていく。昨年の特集上映から着実に歩みを進めてきた結果に何を思うのか、主演の藤原、そして本作ではプロデューサーとして奔走した毎熊に話を訊いた。2人の関係性が滲む写真と合わせてご覧いただきたい。
自分にとっては、ただの映画ではなく居場所の1つにもなっていました(藤原)
バァフ 昨年の特集上映の初日に本作を拝見したので、「この映画を行けるところまで連れて行きたい」という気概に満ちた、舞台挨拶時のみなさんの表情が思い起こされますし、今回〈新宿K’s cinema〉を皮切りに全国へ旅立っていくことも自分事のように嬉しいです。クリスマス時期の舞台挨拶では、毎熊さんがサンタクロースの格好で盛り上げていらっしゃいましたよね。毎熊さんってこういうノリもしてくれる方なんだと思って(笑)。
毎熊 ありましたね(笑)。
藤原 懐かしい。毎熊さん、本当にお忙しい中だったんですが、一緒に舞台挨拶に周っていただきました。
バァフ 11月の『第33回映画祭TAMA CINEMA FORUM』の上映時には、『東京ランドマーク』の今後について、藤原さんから毎熊プロデューサーに質問が飛ぶ場面もありましたが、あの時点では次の上映場所など展開は見えていたのですか?
毎熊 その頃はまだ何も決まっていなかったです。ただ、(藤原が所属する)〈オフィス作〉さんのバックアップの元、昨年の特集上映と、『TAMA映画祭』でも数日間上映することができたので、「この映画をこのまま終わらせるわけにはいかないだろう」と考え続けていました。それで、ちょこちょこ(全国での上映に向けて)動いてはいたんですけど。〈新宿K’s cinema〉さんで、5月18日に上映することが決まったのも今年の3月頃なので、本当に直近です。
僕は子供の頃から「自分で映画を作って上映する」という夢を抱いていましたが、エンガワのメンバーも、季節も真司も本当に付き合いが長いので、この映画に関してはまた少し違った感覚があります。でも、作って満足するのではなく、人に観てもらって初めて報われる、そういう想いはどの作品にもあると考えていて。僕はこの映画に出演していないですし、立場的には絶妙なところですが、第一にやるべきことはたくさんの人に映画を観てもらうことだなと。(プロデューサーの立場は)はっきり言ってド素人なのでいろんな人に教えてもらいながらですが、 まだまだ発展させていきたいと考えています。
藤原 〈新宿K’s cinema〉さんでの上映に続いて、嬉しいことに大阪、名古屋での上映も決まりまして。それも、毎熊さんと(映画にも出演する)大西信満さんが関西まで足を運び、自ら営業して決めてきてくださった映画館なんです。先輩たちの動きを見ていたら、僕も頑張らないとダメだ、引っ張っていかないといけないなと思いますが、実際は引っ張っていただくことばかりで。
毎熊 でもやっぱり これは季節の最大の魅力な気もするけど 季節は言葉を持っているじゃない? 人の心に残る言葉を。この映画の座組は20代くらいの若い子たちで、彼らからすると僕なんておじさんだし(笑)、何て言うのかな……“自分たちにはまとめられない何か”が存在している気がするんです。季節は、その部分を上手くまとめてくれていた。無自覚だったかもしれませんが、主演としての意識が行動に現れていたのではないかなと感じます。
バァフ 藤原さんの初のパーソナルブック『めぐるきせつ』には、〈オフィス作〉の研究生になった20歳の頃、「居場所を見つけられなかった、帰る場所がほしかった」と当時のお気持ちが綴られていました。そして本作の撮影当時、藤原さんは25歳で、この頃はご家族との向き合い方を整理し切れていない時期だったと。孤独や身動きの取れないような想いを5年間抱え続けたまま、『東京ランドマーク』に向かわれたのでしょうか?
藤原 向かったというよりも、気付いたら自分がそこに立っていた感覚でした。特集上映の時、毎熊さんも含む映画の仲間たちが大阪まで来てくださって、舞台挨拶終わりにみんなでお酒を交わして帰ったんですよ。その時に、「ああ、自分の仲間は10年変わらなかったな」と思えたんです。約10年前に毎熊さんに出会い、小劇場で舞台を一緒に経験して、毎熊さん主演の『ケンとカズ』という映画に誘っていただき、そこから僕の俳優人生が幕を開けた。いざ10年経った時、「隣に立っている人、毎熊さんじゃん。あれほど探し求めていた自分の居場所はここにあったんだな」と感じたんですよね。その出会いの中で、『東京ランドマーク』という映画が誕生している。これはとても意味のあることだなと。自分にとっては、ただの映画ではなく居場所の1つにもなっていました。でもきっと、僕だけではなくて、映画を観た人にも自然とそう感じてもらえるような作品になっていると思います。
バァフ 小劇場時代、稽古期間中に20歳のお誕生日を迎えた藤原さんに、その日初めて毎熊さんは声を掛けたそうですが、藤原さんのどういうところが気になったのでしょう。覚えていらっしゃいますか?
毎熊 よく覚えています。シンプルに、お芝居をしている姿に惹かれました。当時おこなっていた作品で、キャストは20人近くいたのかな、僕と季節は深い関係性の役柄を演じていて。ちょっとややこしい話なんですけど、僕が演じる役の“頭の中の登場人物”を他のキャストが演じるので、「ここの芝居はどういう風にすればいいか」とか、みんな色々と尋ねてくるんです。だけど、一番関係性の深い季節だけがほとんど喋らなくて。それなのに、いざ稽古をやってみると通じ合う部分がたくさんあったし、何て魅力的な俳優なのだろうと強く思いました。『東京ランドマーク』で言うと、当時(劇団内に)僕らとは別のチームが2つあって、そこにいた真司も、季節とはまた違う、人の心に残る立ち姿や表情を持つ人で。本当に魅力的な人というのは、人生の中でそう多くは出会わない気がします。それに、好きな人は自分の友達にも紹介したくなるじゃないですか。この映画の始まりもエンガワに2人を紹介したことがきっかけだったので、段々と輪が広がるのは嬉しかったです。
バァフ 藤原さんは当時、毎熊さんをどういう風にご覧になっていましたか。
藤原 今も変わらないですが、「カッコ良いな」とずっと思っていました。稽古前の準備運動をしていた時、大人数の中で1人「めっちゃカッコ良い人がいるな」と思ったのが毎熊さんだったんです。何と形容するのが正しいか分からないですが……ピントが1人だけに合っている感じ、と言いますか。ものすごく迫力もあって。僕を誘っていただいた『ケンとカズ』の完成作を観た時に、「天下を取るな」と思いました。
バァフ 以前毎熊さんにお話を伺った際に、先輩・後輩の関係性が苦手だと仰っていましたが、藤原さんとはそういった距離感とも違う特別な空気が流れているように感じます。お互いへのリスペクトを持った友人、同志のような。
毎熊 僕、あまり先輩とか後輩に好かれるタイプじゃなくて(笑)。エンガワでは多分僕が一番年下なんですけど、他のメンバーのことを僕は先輩だと意識して接していないし、まぁ、そういうのってシチュエーションによっては良くない時もあるじゃないですか。「何だ、俺先輩だぞ!」みたいに言われたり(笑)。でも逆に言えば彼らも僕のことを後輩だと思っていない。同じく季節も、上下関係を意識したことはないんですよね。もしかしたら下の子たちの方が(接し方が)難しいのかな? 上に対して。
藤原 ひょっとしたら、周りが必要以上に緊張しちゃうこともあるのかなと思います。毎熊さんの場合、一見厳しそうな人にも見えるし、実際に厳しい一面をちゃんと持ってらっしゃるので。それは、ご自分に対しても。
毎熊 まぁ、顔が怖いですからね(笑)。
藤原 (笑)でも、付き合いが長くなるほど緊張感というのは突破できる部分だとは思います。
良さに乗っかれなかったら、役者って溺れる気がするんです(毎熊)
バァフ 本作は藤原さん、義山さんの友情関係に興味を持たれた林監督が、お2人に取材をして当て書きをされたとのことですが 25歳当時の境遇や心に渦巻いていた想いが形となって表れる、お2人にとってはある種ノンフィクションのような作品だったのかなと思います。先ほどの質問とも少し重複しますが、お芝居として表出する上で、苦しさや戸惑いはなかったですか?
藤原 あまり感じなかったですが、その理由は、林監督自身がカメラを持って撮影してくれたので、撮られている意識がほとんどなかったからかもしれません。家に2人きりでいる真司と僕の関係がそのまま映画に映り込んだような感覚でしたし、プレッシャーみたいなものもほとんどなくて。ただ、物語の中では、家族や友達というものと本気で関わっていかなければならなかったですし、それは今までの自分が避けてきたところでもあったので、『東京ランドマーク』の物語を通してちゃんと向き合うことを決めたのは僕の覚悟の1つでもありました。もちろんフィクションの部分も大いにあるんですけど、思い切り向き合ったこと自体は苦しかったです。
バァフ 撮影を終えた後は、少し霧が晴れたような感覚に?
藤原 それが、全然なくて。だけど5年経った今は、ちょっとその(霧が晴れたような)感覚があるんですよね。『東京ランドマーク』の存在が本当に大きいと思います。映画が誕生していなかったらエンガワの皆さんと過ごす時間も、今こうして取材でお話しをする時間もないわけで。
この映画の内容にも関わってくるんですけど、多分、稔とタケの生活って、映画のラストで描かれている後もあまり変化がないと思うんですよ。桜子と過ごした時間もたった数日間だった。だけど、その数日が未来の自分たちにとっては、ちょっとした心の支えになるかもしれない。映画を作った僕たちも、ここから自分の人生が劇的に変わるとは思わないです。ただ、ふとした瞬間に背中を支えられる、1つの手にはなれたのかもしれない。そういう想いでいます。
バァフ 毎熊さんは、俳優陣のお芝居を近くでご覧になる中で、過去のご自身を重ねるような瞬間はありましたか?
毎熊 僕にも稔とタケのような関係の親友がいますし、何でもない時間を一緒に過ごした自分の実体験ともリンクする部分は多々ありましたが、実はそれって、計算してもなかなか切り取れるものではないと思うんですよね。撮影に入る前、「どういうスタイルでやっていくのか?」などいろんなことをチームで相談して、僕は一歩引いたところからみんなを見ていたのですが、「もう少し準備に時間をかけて撮影に入った方が良いんじゃないか」と感じていました。でも、季節と真司、林監督には、共に重ねた時間がすでにたくさんあって、今じゃなきゃダメなんだと力説されたんです。結局そのまま撮影に入りましたが、当時の僕はいまいち理解できなかった。そして5、6年経った今、改めて作品を観たら、「あの時にしか撮れなかった映像だ」と明確に分かったし、タイミングが合致した時 そのタイミング自体も一期一会で しっかりと“瞬間”を切り取れているなと思えたんです。奇跡的ですよね。もし3ヶ月後だったら破綻して撮れなかったかもしれないし、それより早くてもダメで。映画にはそういう奇跡があるんだなと実感しました。
一歩引いたところで2人を見ているとね、季節と真司って不思議な関係なんですよ。で、僕もそうですし、関わっているエンガワのメンバーも、そんな2人のことが大好きだから映画が生まれた。自分たちが「好きだな、こしょばいな」と思うものが全部映っているんですよね。
バァフ 仰るように、誰かが誰かを想いながら誠実に作られたことが受け手にも伝わる映画だと思います。それが、稔、タケ、桜子の間にも表れていて。すべての現場で実現できることではないと思いますが、物作りに携わる人間としては羨ましく観ていました。
藤原 僕は、仕事を一緒にしてくれる人たちをとにかく信じるのが一番大事だと考えています。小劇場時代、舞台の外でディスカッションをしなかったのは、僕だけでなく毎熊さんも同じだったんですよ。でも、僕たちの間には目に見えない信頼関係みたいなものが存在していた気がして。現場で自分の理想通りに動いてもらいたくても、色々な都合上、難しいことが山ほどありますが、それでも議論を起こし波風を立てながらも良質な作品を作ることができる人もたくさんいると思うんです。でも、僕はどうにもそれが苦手みたいで。よく誤解されるんですけど(笑)。議論をするよりも信じて待てば、1つの方向を向ける瞬間がくるんじゃないかなと。これはあくまでも僕の理想でしかないですが、ただひたすらに待つことを心掛けるようにしています。時間を要する場合もあるし、最後まで同じ方向を向けないこともある。それでも5年経って、初めてみんなが同じ方向を向けることもあったりするので、不思議なものですよね。毎熊さんはどうですか?
毎熊 僕はなるべく無で臨むようにしています(笑)。何だろう、無というか、1つの価値観で挑んでしまうと、そうじゃない良さに出会った時に逃してしまう可能性があると考えていて。『東京ランドマーク』で感じた良さ、僕で言ったら『ケンとカズ』で感じた良さは、現場の熱量や作り方としては1つの形だった。でもそれが理想なのではなくて、いろんな良さを発見できる方が「溺れずに済む」と言えるのかな。良さに乗っかれなかったら、役者って溺れる気がするんです。「1人だけ微妙な奴がいたな、理由は分からないけど」みたいに、フィルム上で何となくバレてしまう。だから、一期一会でその場に集まった人たちから生まれる良さを、自分で発見していくのが大事で。季節と同じく、信じて待つこととも近いのかもしれません。
バァフ 終了のお時間が迫ってきたので最後に……印象的だったシーンが本当にたくさんあるのですが、中でも食事のシーンが多く描かれていた印象で。物語冒頭の、稔が桜子に振る舞う茹でただけのシンプルなパスタ、河原のバーベキュー、稔、タケ、桜子で囲む鍋、顔を見せにきた息子(タケ)にわざわざご飯を作ってくれる父親。シチュエーションも関係性も違えど、そのいずれにも、情というものが流れているなと感じました。そして、稔にしたらお金もないギリギリの生活だけど、最低限の食事をして、かつ他人にも分け与えている。不安定な日々ながらも、食べ物を摂取し命を繋ごうとする行為が、明日も生きるぞという意欲や希望のように思えて。これは、意図的に取り入れた部分だったのでしょうか?
毎熊 どうなんでしょう。おそらく、一番良い答えを導き出せるとしたら林監督なのかな。
藤原 お話を聞いて思うのは、今って機械がご飯の量を調節してくれたり、お肉の焼き加減を良い具合に調節してくれるお店が多いじゃないですか。そういうものを食べるのと、劇中のように誰かの手で作ったものを食べるのとでは、食べた後の満足感や安心感って気持ち的に少し違いますよね。そう考えると、『東京ランドマーク』は確実にみんなが自分たちの手でこねた1つの作品だなと感じます。観た後の温かさは、ひょっとしたらシネコンの映画にも負けないかもしれない。
毎熊 そうだね。生きている限り食事は絶対におこなうものだし、茹でたパスタに塩だけをかけて食べるみたいなことって、全員とは言わずとも結構みんな経験があるんじゃないかなと思うんです。白米にふりかけだけとか。でもそれは、生きていく行為でもあるし、家庭を連想させるものでもあって。料理とも呼べないものを作る=表面的には見えづらい愛情というか。感覚的な問題だから、林監督がニュアンスで入れている部分かもしれないですが。『東京ランドマーク』はそういう要素がたくさんありますよね。例えば、稔の父親の姿は劇中に1回も出てこないし、息子をどう思っていたかとかも全く描かれていないけれど、何かは感じる。映っていないところからも感じ取れる要素がたくさんある、その良さがこの映画には溢れていると思います。

©Engawa Films Project 2024
『東京ランドマーク』
脚本・監督・撮影・編集/林 知亜季
出演/藤原季節、義山真司、鈴木セイナ、浅沼ファティ、石原滉也、巽 よしこ、西尻幸嗣、柾 賢志、幸田尚子、佐藤考哲、大西信満
5月18日より〈新宿K’s cinema〉にて、7月6日より〈大阪第七藝術劇場〉、〈名古屋シネマスコーレ〉にて公開
【WEB SITE】
INFORMATION OF KISETSU FUJIWARA
『ケンとカズ』を手掛けた小路紘史監督による、8年ぶりの完全自主制作映画『辰巳』に出演、全国公開中。
【WEB SITE】
www.office-saku.com/artists/new_actors/kisetsu_fujiwara
【Instagram】
【X】
INFORMATION OF KATSUYA MAIGUMA
出演するドラマ『好きなオトコと別れたい』が、毎週水曜深夜0時30分より〈テレビ東京〉系にて放送中。
【WEB SITE】
alpha-agency.com/artist/maiguma
【Instagram】
【X】