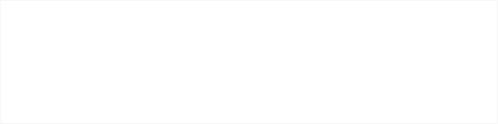CULTURE







昨年公開された映画は6本、今年も現時点で6本の映画が公開&発表されている俳優の中島 歩。テレビ・ドラマもコンスタントに出演するなど活動が目覚ましいが(5月23日から〈TBS〉系ドラマで初レギュラーとなる『スイートモラトリアム』にも)、本人はと言えば、今が踏ん張りどころ、といった佇まい。5月6日から公開される映画『さいはて』(越川道夫監督)の撮影も、「大変でしたー」といつものスロー・トーンで素直に振り返る。
「映画やったなって気がします。映画作ったな、と」と中島が語る本作は、夜の飲み屋で知り合ったモモ(北澤 響)という若い女性と、塾の国語教師・トウドウ(中島)が、今いる世界から逃げ出そうと、船に乗って海を目指す物語。2人は一体どこへ向かうのか? 哀愁漂うどこかほつれたロード・ムーヴィーと2人の恋愛模様が映画としての輪郭を引き立たせ、観ている時間はまさに映画の世界に逃避行できる、そんな作品となっていた。小説の一編のようなセリフ(実際、フラナリー・オコナー『賢い血』など幾つかの小説が引用されている)と独特な言い回しに中島は苦労したようだが、生きる気力を無くしたトウドウという男性のくたびれ加減を中島は自然と体現しており、彼がインタヴュー中に何度も「疲れました」と言っていたのは役をまっとうした証ではないのだろうか、そんなことを思いながら話を聞いた。
好きでやっているものというのは作る必然があると僕は思っていて、作る必然がある映画というのは——映画に限らず、音楽でも絵画でも——強い作品になると思っています
バァフ 完成した作品をどうご覧になりましたか?
中島 濡れ場が多いので自分としてはあまり観ていられなかったんですが、頑張ったなぁとは思いました。
バァフ 「映画を観た」って感じになれる映画でした。
中島 あぁ。まずやっぱり、ロケーションがいいですよね。相模湖と九十九里浜に行ったんですが、ロード・ムーヴィーにもなっているところが気に入っていますし、そういうところが「映画らしい」のかもしれませんね。
バァフ 「また湖がきた」とも思いました(笑)。
中島 確かに(笑)。『アレノ』(2015年公開の越川監督の作品)の撮影も相模湖だったみたいです。
バァフ 撮りたいテーマと湖がどこかリンクするのかもしれませんね。監督の作品にどんな印象がありました?
中島 それこそ『アレノ』は当時劇場に観に行きました。湖が印象的な映画で、作品のトーンも今回と近いですよね。行き詰まっている人たちの話、というところで。越川さんは映画そのものに対しても、映画を撮ることに対しても、すごくロマンを持っているロマンチストだと思います。あと俳優に対してもロマンチックに思っていて、僕と北澤さんの間で起こる何かマジカルなことをずっと信じて芝居を見られていた気がします。
バァフ 監督の描くテーマは一貫性がありますよね。これ自体をどう捉えられていますか?
中島 大変だな、とは思いました。行き詰まる状況に自分を持っていかないといけないので、撮影はかなり消耗するだろうなと。実際そうでした。行き詰まる状況をイメージしていく、実感していく過程が大変というか。
バァフ 今の時代も行き詰まった人や息苦しさを抱える人が多いとは思いますが、監督が描く世界観、今回で言ったら男女の逃避行という形を取るケースは何となく少ない気がして、そこがやはりロマンを感じる点でした。
中島 行き詰まっているのはとっくにそうで、僕のイメージでは、こういう映画も2、30年くらい前からある気がします。時代という点で言うと、今はから騒ぎのような時代で、行き詰まっているのが当たり前の状況でどんどん状況が悪くなっているからこそ、楽しまないとやっていけないというノリを、特に今の若い人、20代前半の人からは感じますね。劇中でも「ただ楽しめばいいんですよ」というセリフがありますが、自分が言いたいことのように思ってしまうくらい、印象的なセリフでした。
バァフ ただ楽しむのも難しい気がしますが、例えば中島さんは芝居をただ楽しめていますか?
中島 そんなことはやっぱりないです。疲れるし、苦労もしますし(笑)。あと気を遣いますよね、現場にいるといろんな人に。もちろん相手役の人、演出家がいて、カメラの段取りがあって、メイクさんや衣装さんへの気遣いもあるし。それらをひっくるめて、僕はこの仕事が楽しいと思っていますけど。そう言いつつも、そんなに苦じゃないから(笑)。非常に疲れますが、割とただ楽しんでいるところはあります。最近特にそう思いますね。「遊んでいる」と言うと語弊があるかもしれないけど、仕事と思わず遊んでいる感じがします。というかずっとそうだったし、そのつもりでこの仕事を始めたのですが、最近また気付いて、ふざけた芝居をしていました。監督やプロデューサーにまた声をかけてもらわなきゃと思っていたら、こんなバカなことはできないな、と先週くらいに思ったんです。やっぱり僕はバカで、遊ぶのが前提として好きなのかもしれません。
バァフ 遊ぶというのはアドリブをするとか?
中島 アドリブはもちろんあります。そもそも「お芝居が楽しい」というところから始まっていますから。僕は一時期、一番遊んでいる人たち——役者の世界で馬鹿げたことを楽しんで一生懸命やっている人がいて、そこに居場所を感じてその人たちと20代の頃、ずっとつるんだりしていたのですが、それを今、現場でできるようになってきている感じです。で、越川さんも、ロマンチックという言い方をしましたけど、そういう人ですよね。お金になる仕事を越川さんも僕もしますけど、この作品は好きでやっているもの。好きでやっているものというのは作る必然があると僕は思っていて、作る必然がある映画というのは——映画に限らず、音楽でも絵画でも——強い作品になると思っています。特に今回は撮影前、越川さんの映画の仲間がどんどん亡くなっていて——青山真治さんとか、立教の同級生ですから。これを撮る必然が越川さんの中にあったという話を聞いたんです。「僕もどうなるか分からないから映画を撮らなきゃいけないんだ」と。年齢の近い友人の死があったことでそういう想いに駆られた。この前後に越川さんは3、4本撮っていますから、それはもう、すごい衝動に駆られているわけですよ。しかもあの歳でこの量の作品を作るっていう。今回の撮影もハードでしたから大変だったと思います。その想いに報いるのも大変でしたが、その分、強い映画にはなっていると思います。
バァフ そういう熱量が伝播して中島さんも奮い立てたのか、それよりも疲弊の方が強かったのか。
中島 いやぁ、もう、「用意ドン!」と言われたら(俳優は)走るしかないので(笑)。あとね、北澤さんがまだ若いから、元気なんですよ。
バァフ 中島さんだってまだ若いじゃないですか。
中島 そうなんですけど、僕はこの撮影の時くらいから、疲れを実感するようになったんですよね。年齢もあるし、仕事も増えたし、歳を重ねると、色々と気付くことが多いじゃないですか。体力は落ちているのに気付くことは増えるから、どんどん疲れていくみたいな(笑)。
バァフ (笑)全編で印象的だったのは、モモは直接的な触れ合いをトウドウに求める生命力の強さみたいなものがあるのに対してのトウドウのくたびれ加減のコントラスト、これが図らずも作品のテーマにリンクしているのかなって思いました。
中島 なるほど。
バァフ トウドウは本当に生きるのに疲れた感じが中島さんの全身から滲み出ているんだけど、モモは「私は焼け野原です」と言ってはいるものの、どんどんトウドウに惹かれて一緒にいたい気持ちが募っていって。
中島 (監督の)そもそもそういう意図だったでしょうし、彼女の存在が映画の心臓になっていると思います。
バァフ 例えば冒頭の「夜が怖くて怖くて仕方ないんです」と言うトウドウのセリフがありますが、あのセリフの言い回しとか、難しいですよね。
中島 そうですね、かなりリリカルなセリフだったと思います。難しかったですね、やっぱり。
バァフ 越川監督の作品は文学的と言われることも多いですが——勝手ながら中島さんは下駄を履いていそうなバンカラ感とか文学青年感があるので、妙にこういった役がハマるなと。一方で、『岸辺露伴は動かない』みたいなトリッキーな見栄えの役もハマる振れ幅が中島さんは面白いなと思うのですが、トウドウの自分に浸っている感じを見事に体現されているなと思いました。
中島 (笑)いやいや。まぁ、セリフのことで言うと、難しいですよね、こういうセリフは。言えていない時がよく分かる。だけどそれも含めて逆に真実というか、俳優が言えていない事実を、上手い現代口語で書かれたセリフなら何となく言えて、誤魔化せると思うのですが、こういうリリカルなセリフだと、「あぁ言えなかったんだ」というのが分かる。観ている人にも。そういう意味で、嘘が逆に無くなるのかな、と今ちょっと思いました(笑)。僕がこういう役が似合うかどうかは分からないですけど、どんな役であろうと、『岸辺露伴〜』の時のような役であっても、「この人にやってもらおう」と自分をキャスティングしてもらった時点で、似合わない役なんてない、僕がやるんだから、と思います。だけど、役と自分との間に距離はあります。今回はちょっと(距離が)あったと思っていますが、でも、どうだろうなぁ。距離がまったくなかったとも言えません(笑)。(自分も)こうなっちゃうかもな、とは感じましたもんね、やりながら。嫌だな、こうなっちゃったら、って。
バァフ 男女の逃避行ものって、男性作家が描くイメージがあって、やっぱり男性の方がロマンチストなんだなと思ったりもしました。だって飲み屋で若い女の子と知り合ってそのままって、夢があるじゃないですか。
中島 もしかしたらこういう状況に俳優という人間を置くのが(監督は)好きなのかもしれないですね。じゃないとマジックなんか生まれないんじゃないですか。
バァフ マジックとは違いますが——しかも笑うポイントでないのは承知ですが——観ていて思わず笑ってしまったのが、トウドウが海に入っている場面で、モモに「もっと真面目にやれ!」って怒って叫ぶんです。このやり取り何だろう? 生きている感じがするなって(笑)。
中島 (笑)青春ですよね。
バァフ 現場ではどうだったんですか?
中島 笑っちゃっていますよ、真剣だけど。もう帰りたいよって気分でした(笑)。あんな寒い海の中で。
バァフ しかも、普段怒鳴らない人が怒鳴るとこういう怒鳴りになるんだろうなっていう怒鳴りで。普段から怒鳴る人の貫禄や怒気がないっていうか、怒鳴り慣れている人って、声のハリも違うじゃないですか。
中島 あぁ(笑)。なんか恥ずかしいですね。
バァフ そういうのも含めて、トウドウの繊細さと軟弱さが中島さんにハマっていたなと。ところでお話をお伺いしていると、作品数も多くてお疲れのところもあるのかなと思ったのですが、楽しさと大変さのバランスを中島さんはどう取られているんですか?
中島 いや、取れていないんじゃないですか。疲れきっちゃっているから。なんでしょう、例えば現場に行って、「あぁ機嫌悪いなこの人」という人がいた時に、励まそうっていうか、機嫌を取るかって気になる余裕がある時もあるかもしれないですが、その余裕もない時はやっぱりあって。で、撮影現場って本当に気が散るんですよ。ただ、それも含めて集中なんだ、と先輩に教わった時、なるほどと思って。後ろに誰かが立とうが、物が落ちようが、例えばこの撮影の時(と言って映画のある場面写真を指す)ハチが飛んでいるんですけど、ハチに刺されようが、それ含めて集中なんだ、と。で、ある時からそれが実感できるようになったんです。そうしたら、余計な力が抜けたんですよね。そういうの、全部含めて撮っているから、仮に後ろでゴンって大きな音がしても芝居は続けられる。要するに全部を受け入れると、いろんなことを含めて芝居ができるようになった。そうすると、ちゃんとそこにいる人に見えてくるんですよね。それがここ数年で分かるようになりました。
バァフ 余裕が生まれたからこそ、さっきおっしゃったように、芝居でふざけるというか、要するにいろんな芝居をする幅が生まれてきた、ということですか?
中島 アドリブに限らないですけど、例えば「大好きだ」というセリフでも、「大好きだ」という言い方と「大好きだ!」(と大きな身振りをする)という言い方と、色々あるじゃないですか。なのでそうですね、振り幅が広がったところはあるかもしれません。多分人って、このくらい表現の幅があるとしたら(と言って自分の手で幅を見せる)——ボリュームなり機嫌なりテンションなりが。みんな芝居になるとこのくらい(と言って狭める)になっちゃう。一生懸命になるから。「あなたもっと普段楽しそうなのに」とか「もっと大きな声が出るのに」みたいな。だけど力が抜けると、振り幅が広がる。場合によっては、役によっては、自分の基準が100だとしたら120だとか160くらいの自分が出てくることもある。昔、ある尊敬する演出家に、「中島くんはテンションがすごく低い方だけど、にしても、もうちょっと普段は元気だよ」と言われたことがあって。芝居になると、もっとテンションが低くなっちゃうところがあったんですよね。現代口語劇のただ喋っているみたいな場面って最近よくあると思うんですけど、みんなそこに陥ると思うんです、大体の俳優が。何気ない芝居でしょ?みたいなところで芝居をしてしまう気がする。今喋っているように、セリフでも、相手の話を聞いて、セリフを言えるようになってきたのかなと。セリフのやり取りと普段の会話と、近くなってきた感じはしますね。だからその、やっぱり芸事だな、と思います。そういったお芝居を初めからできる人もいるのでしょうけど、経験を積んで、勉強をして、演出家にいろんなことを言われて、友達とかにも色々言われて、変わっていくと、続けるだけのことはあるなと最近思います、演技に対して。芸事だなぁと。
バァフ 現場や監督によって、求められるものが違いますよね。どんな場でも自分のスタイルを貫ける人と、現場によって芝居のスタイルも変える人と。現時点で中島さんの俳優としての自己像はどんな感じですか?
中島 自己像の話じゃなくなってしまいますけど、僕が今思っているのは、芝居をしているのは、セリフを言っているのは、事実だから、それをセリフじゃないように言うのは、むしろ嘘が1個増えるんじゃないか、と。セリフを言っているのだから、セリフのままでいいっていうか。だから今回みたいなリリカルなセリフだと、セリフを言っていますということが分かるから、嘘が1個少ないんですよ。あとは、『偶然と想像』をやらせてもらった時に感じたのは——濱口(竜介)監督というのは、俳優の意図を極力削いでいく演出をされているなということで。俳優がセリフを言っているところをカメラで捉える、それをまず誤魔化さない、嘘をつかない。その地点から始めている。で、その場で俳優が何かセリフを言い合っていると、その時に何か起こるようになっているんです。濱口監督の場合は本当に戯曲を作るのが上手だからそれができるのだと思いますけど。セリフだけどコミュニケーションしたよっていうのを撮る。それをテーマにした映画が『ドライブ・マイ・カー』だと僕は思っていて。演技のコミュニケーションそのものをテーマにしている。だからあれはコミュニケーションについての映画ですよね。演技でコミュニケーションが可能か?っていう。そういったところからも考えるのは、そういう真実は真実としてある、だって演技をしているんだから。だったら面白くしたい、というところをやっているつもりです。やる以上は、お客さんが突っ込む間だったり、笑いやすいテンポや間だったりを考えて、ちゃんと芝居として見せる、ということを、最近は特にやっていた気がします。ただリアルにやるという方向よりも、観ている人が楽しいだろう、という方向に寄った芝居ですね。
バァフ いろんな方がよく言うことですが、笑いを狙って芝居をすると面白くならない、と。先ほど言った海のシーンはきっと狙ってやったものじゃないですよね。
中島 そうなんですよ。特に映像だとウケなくて。だから笑わせよう、という意図だけじゃなくて、この役がどうしたいのか?という意図に俳優自身がちゃんと向かっているのがまず前提としてあって、でもどこかでエンターテインメントしないといけない、そのバランスなんだと思います。エンタメに行き過ぎると、「この人笑わせようとして寒いな」ってなるし、リアリティみたいなものに寄ると、説得力はあるかもしれないけど退屈になっちゃったりもする。そのバランスに気を付けながらやっています。最近はこっち(エンタメ)に行き過ぎて自分の芝居が安っぽくなっちゃっているんじゃないかっていう不安もあるんですけど(笑)。「ふざけ過ぎだろう、お前は」って。インタヴューとして喋っているから何か真っ当な話のように聞こえるかもしれませんけど、おばあちゃんが観たら、「あんたカメラの前でこんなことして大丈夫なの?」と心配すると思います。
バァフ 日本人でも海外の俳優でも、この人の芝居にはつい笑っちゃうな、という人はいますか?
中島 いますいます、いっぱい。誰だろう? アダム・サンドラーとか。あの人がすごいのは——映画でたまにものすごくサーヴィスしちゃう時もあるんですけど、そしてそれはあまり面白くないんですけど——その役の意図に則ってやっているんだけど、やっぱりどこかでサーヴィスしているところがあるんです。そのバランスが好きです。結局人柄が可愛いっていう話でもあるんですけどね、そういうのって。思わず笑っちゃうとか、笑ってしまう雰囲気があるのを、落語の用語で「フラ」と言うのですけど、フラのある俳優、誰だろうなぁ。他はすぐ出てこないけど、そうなりたいと思いますね。
バァフ アダム・サンドラーと言えば『アンカット・ダイヤモンド』で相当イラつかせてもらいましたけど。ちょっとした笑いとイライラしかない映画(笑)。
中島 すごい組み合わせですよね。(ジョシュ&ベニー・)サフディ兄弟(監督)とアダム・サンドラーって真逆の感じだけど。だってサフディ兄弟のその前の作品、『グッド・タイム』って観ました? すごいですよ。いやでもほんと、最近は観ることから遠ざかっていたので、話す引き出しがないんですよね(笑)。
バァフ 海外ドラマなども観ていないですか?
中島 はい。あ、でも、(ニコラス・ウィンディング・)レフン監督の『コペンハーゲン・カウボーイ』は観ました。ああいうのが好きです。しかも出ているの、素人ばっかりですからね(笑)。

『さいはて』
監督・脚本/越川道夫 出演/北澤 響、中島 歩、金子清文、美香、杉山ひこひこ、君音、内田周作、他
5月6日より〈K’s cinema〉他、全国公開
©2023 キングレコード
【WEB SITE】
mayonaka-kinema.com/saihate/
INFORMATION OF AYUMU NAKAJIMA
映画『遠いところ』が7月7日より、『17歳は止まらない』が8月4日より、『さよならエリュマントス』が8月11日より、『スイート・マイホーム』が9月1日より公開。〈TBS〉系ドラマ『スイートモラトリアム』が5月23日より放送。
【WEB SITE】
tencarat.co.jp/nakajimaayumu
【note】
note.com/ayumu_nakajima