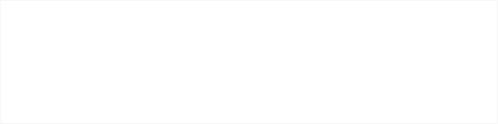CULTURE


鬼束ちひろを見出した音楽プロデューサーが回想する出会い、楽曲の驚き、存在の特異さ、そして、いかに世に出そうと奮闘した日々
APR. 24 2024, 6:00PM
2000年、19歳のシンガー・ソングライター、鬼束ちひろの登場は衝撃だった。初めて聴いた瞬間、とてつもないソングライティングの才能、素晴らしいヴォーカリゼーション、そして、曲を創り、歌うことでしか居場所を見つけられない圧倒的な表現者の佇まいを感じざるを得なかった。
それから24年、第一線で表現活動をおこなってきている彼女だが、この3月、『インソムニア』、『This Armor』、『Sugar High』と初期3枚のアルバムのリマスター音源に、デビューのきっかけとなった初オーディション時に録音された生歌唱音源、未発表カヴァー音源、アルバム未収録楽曲を収録したスペシャル・トラック集の4枚組CDに、2003年1月3日〈NHK総合〉で放送されたドキュメンタリー番組『神が舞い降りる瞬間~鬼束ちひろ・22歳の素顔~』の映像DVDに、デビュー前、カセット・テープに弾き語り録音したデモ音源3曲を収めたカセット・テープで構成されたボックス・セット『UN AMNESIAC GIRL ~First Code(2000 – 2003)~』をリリースした。
このタイミングで、当時、〈東芝EMI〉(現・〈ユニバーサル ミュージックジャパン〉)子会社〈メロディー・スター・レコーズ〉の代表で、オーディションで彼女を見出し、音楽プロデュースからマネジメント、販売戦略とすべてをおこない、3枚のアルバムを制作した、現在、音楽ビジネス・コンサルタント、A&Rプロデューサーの土屋 望と、デビューからバァフで取材、連載をおこない、2001年リリースのシングル『infection』からCDのアートワーク、ミュージック・ヴィデオ、ライヴ&TV番組出演時のスタイリングと、すべてのヴィジュアルをディレクションしてきた山崎が、その才能、特異な存在について語り合った。
この17歳はもう今の時点で人生の真実に到達して、人生を表現しちゃっているなと
山崎 鬼束さんとの出会いは、遡ること20何年前ですよね。
土屋 そうですね。僕が、初めて本人と初めて会ったのは確か1998年とかだと思います。オーディションでした。
山崎 当時の土屋さんはどこに所属されていたんですか?
土屋 〈東芝EMI〉(現・〈ユニバーサル ミュージックジャパン〉)内の〈Virgin TOKYO〉という、イギリスの〈ヴァージン・レコード〉の日本のブランチを任されていました。同時に、それを運営する〈メロディー・スター・レコーズ〉という別会社も立ち上げて。六本木にオフィスを構え、そこで新人専用の舞台としてやっていたんですよね。何にもコンテンツがないので「新人オーディションからやっていきましょう」と、今考えたら信じられないですが、そういう状況でした。
山崎 そのオーディションに鬼束さんが応募してきたと。
土屋 そうです。厳密に言うと、レーベルの3回目のオーディションの応募者です。というのも いつだか忘れちゃったんですけど、真夜中にレーベル仲間の外国人(John Possman)が僕のオフィスを訪ねてきたことがあったんです。彼は〈Virgin DCT〉という、DREAMS COME TRUEのレーベルの責任者だったんですけど、彼がお客さんを連れて来たんですよ。そして何とその人は、当時の〈ヴァージン・レコード〉本社のトップだったんです。
山崎 夜中にノーアポで本社のトップが来るとは(笑)。
土屋 そう。「マジで?」となりますよね(笑)。明日からのカンファレンスのための来日で、今夜はお忍びで来たと。で、僕はかなり驚きながらも、その場で頭に浮かんだジャスト・アイデアを彼に伝えました。「今、私達は新人を見つけるためにオーディションをやっています。その募集告知のヴィジュアルに〈ヴァージン・レコード〉のインターナショナル・アーティストのアーティスト写真を使えませんか?」と直談判したんです。なんだかカジュアルで気が良さそうな人に見えたので(笑)。そうしたら、「全然いいよ!」と言ってくれて。「やった!」と思いましたね。それまでは、勝手に使ったら怒られるだろうし、そもそも洋楽の人からアーティスト写真をもらうのも大変で。でもトップからOKをいただいたので、ジャネット・ジャクソンとか、ローリング・ストーンズ、スパイス・ガールズ、レニー・クラヴィッツなど、当時売れていた〈ヴァージン〉のアーティストたちを全部募集広告に載せました。そして、その写真を見て応募してくれたのが鬼束だったんです。
山崎 そういうことだったんですね。
土屋 これ、今、初出しだけど、きっかけはこういうことがあったからなんです。
山崎 それで彼女がテープを送ってきたわけですが、聴いた時のファースト・インプレッションはどんなものだったんですか?
土屋 聴く前に、テープに曲名が書いてあるじゃないですか? それが、ジュエルという若いカントリーのアーティストのものだったんです。日本でもそんなに注目されているアーティストではなかったので、まずジュエルを歌ってきたことにとても関心を持ちました。17歳だったし、宮崎県の聞いたこともないような町に住んでいる10代の少女が何でジュエルのカヴァーを?と思いました。他のテープは、当時流行っていた邦楽が多かったからすごく目立っていた。気になりながら歌を聴いたら、すごく落ち着いた声で。とても17歳には思えないような、申し訳ないですが、率直に言うと、ちょっとおばさんっぽい声質でね。歌いこなしているんですよ。それを聴いてますます気になりました。
山崎 入っていたのはその1曲だけ?
土屋 そう。
山崎 オリジナルじゃなくカヴァーだけだったと。そのカヴァー1曲だけで、どうしてコンタクトを取ろうとまで思ったんでしょうか?
土屋 何かわからないけど気になったとしか言いようがないですね。僕は音楽担当だったのでテープを聴くだけだったけれど、宣伝部のみんなは写真や応募動機なんかも見てるんですよね。その中で「この子は良さそうだな」とか、「直接会ってみたい」と思った人に声を掛けて呼ぶという形だったんです。今と違ってアナログな応募形式なので、郵便局の人が抱えてきたサンタクロースみたいな袋にたくさんの封筒が入っていて、それを1つずつ開けていました。で、実際のオーディションでは面接は宣伝のスタッフが担当して、僕はスタジオで彼女の生歌を聴いて、落ち着いた歌声、堂々とした佇まい、そして見た目は普通の17歳の少女、というギャップにやられました。ちなみにその時の歌もジュエルだったんだけど(「Who Will Save Your Soul」)、その時の実際の音源が今回リリースされたボックス・セットのDisc4に収録されています。
山崎 目の前に立つ本人はどんな子だったんですか?
土屋 緊張していてあまり喋らない印象でした。ルックスはオーガニックに可愛かった。ただ、目だけ据わっている。それも僕はすごく気になって。良い意味で、目が据わっているんです。歌を歌っているだけで、それ以外はほぼ喋っていなかったと思います。
山崎 オーディション以降、どのタイミングで彼女のオリジナル曲を聴いたんですか?
土屋 詳しくは覚えていないんだけど、オーディションって段階があるじゃないですか? 確か、1次オーディションの後に、今度はこちらの意図で、「こういう曲歌えますか?」と練習してもらってまた披露しに来てもらう流れがあったんです。その時に、本人がモジモジしながら「実はオリジナルをちょっとだけ作っていて」と言ってくれたので「聴かせて聴かせて!」と。その場にあったキーボードを弾きながら歌って。それが後に1stアルバムに入る「call」という曲の英語詞の原曲でした。すごく良かったので、「何でオリジナル曲をやらないの?」と伝えたんですが、本人は自信がなくて「いや、全然です」という感じだったんですよね。でも曲は結構作っていたようだったので、「どんどん送ってよ!」というやりとりをしていました。英語の歌詞ばかりで、日本語詞が1つもないんです。「恥ずかしい」って。僕は絶対日本語で書いてもらいたいと強く思って、何度も「日本語で作ってみなよ」と言ってました。
山崎 最初の日本語詞の曲は覚えていますか?
土屋 覚えていますよ、それも「call」でした。めちゃくちゃ良かった。いろいろ衝撃的で。(彼女にとっては)「生きる」イコール「歌う」ことなんだなと。呼吸するように歌っているというか。歌詞ももちろんだけど、この子は生きていくための手段が「曲を作って歌うこと」しかないんだろうなと、勝手に感じ取っていて。いろんな音楽を聴いてきた中での直感でしたが、この17歳はもう今の時点で人生の真実に到達して、人生を表現しちゃっているなと。最初の日本語のオリジナル曲を聴いた時、強烈にそう思いましたね。
山崎 未熟ではなく、最初から。
土屋 最初から到達している。荒削りですよ。だけど人生の真実を17歳そこらで切り取って表現しちゃっているなと。僕は緊張というかプレッシャーというか、どうやって世の中にこの存在を、あるいはこの歌を、どの順番で届けていけば、居場所ができるのだろうか?と。その他のスタッフには一切言わなかったけど、そこに取り憑かれていた感じはありましたね。
山崎 時代を見ると、同じ社内から先に宇多田ヒカルさんと椎名林檎さんがデビューしてブレイクしていました。
土屋 ちょうど彼女と僕が会う直前くらいに林檎ちゃんがデビューして、その半年後くらいにヒカルちゃんもデビューして。
山崎 お2人以外にも、女性アーティストが台頭した90年代後半でしたよね。その状況の中で鬼束ちひろというアーティストをどう世に出そうか?と。
土屋 先ほども言いましたが、この子がそこに存在して歌を歌うだけでもう個性なので、プロデューサーとしては、とにかくそのまま世の中に伝えるだけだと思っていました。ただ、方法や順番、それは色々と考えなきゃいけないなと。あと、普通は「こういうサウンドでいこう」なども考えるのですが、そちら側にはあまり気持ちがいかなかったですね。
山崎 土屋さんの立ち位置が特殊だったんですよ。子会社の代表なんだけども、音源制作もやるし、マネジメントもしていて。戦略も作って、本社とのリレーションもおこなってと、他にいないですよ。
土屋 冷静に考えると気が狂っていたなと思うけど、気が付いたらそうなっていて。若さや怖いもの知らずということもあると思うけど、普通なら絶対にできないような打ち手をたくさんやったというのは結果的にはあって。ただ、必死だっただけなんだけどね。とにかく何かの足跡を残さないといけない。その気持ちは強烈にありましたね。
山崎 今でも覚えているのは〈SHIBUYA TSUTAYA〉の下のカフェで、文字がめちゃ大きい企画書を手に、熱く語る土屋さんの姿がそこにありました。
土屋 〈SHIBUYA TSUTAYA〉で展開した時、タイミング悪く本社の意思決定と全く逆のことをしてしまって。というのも、ちょうど〈TSUTAYA〉さんがレンタルからセルも始められるということで各レコード会社と取引条件の交渉をする中で、〈東芝EMI〉は、条件が折り合わず当初は直取引をしない(卸会社を通じてのディール)と決めたんです。ちょうどその直後に〈SHIBUYA TSUTAYA〉がオープンして。僕はその取り決めを知らなくて、スタッフを〈SHIBUYA TSUTAYA〉に売り込みに行かせたら、バイヤーが乗ってくれたというシンプルな話なんだけど。彼らも渋谷のスクランブル交差点のところに旗艦店として〈SHIBUYA TSUTAYA〉という店を出し、自分達の媒体力がどれくらいあるか?を世間にアピールしなきゃいけないタイミングで、鬼束という無名の新人を売り込まれて、バイヤーの方々も好反応という純粋で良い話だったんだけど。でも本社からすると、子会社が勝手に営業をして、会社の取り決めを無視しているという見え方になってしまうじゃないですか? それで僕は鬼のような顔をした営業担当役員をはじめ、いろんな方に怒られるという(笑)。
山崎 (笑)デビュー時の展開と言うと、大きいフリーペーパーも作っていましたよね。
土屋 色々と作りました。デビュー・シングルの受注が全く振るわずで。「このアーティストを応援してくれる拠点店が、今のところ見つかっていない」という通達が本社からデビュー3ヶ月前くらいにあったんです。それを受けて「このままでいるわけにはいかない」と必死で動いた矢先の出来事でした。
山崎 ということは、当時は本社も、「大々的に売るぞ」というスタンスでは全くなかったと?
土屋 とんでもないですよ。「地味だな。大事なデビューにこんな暗い曲で大丈夫?」みたいに思っていたんじゃないかな。 最初は協力体制のもとに進める感じではなかったのを覚えています。でも僕は何をもってしても、彼女の曲を世の中に出して、最初の楔を打ち込まなきゃいけないと、ただそのことだけにフォーカスしていました。
山崎 拠点を作っていこうとしたり、フリーペーパーを作ったりするゲリラ的な行動って、まさにインディーズの動き方なんですよね。
土屋 マインドも置かれた場所もインディーズでしたね。山崎さんが出している『バァフアウト!』に話を持って行った時のことも覚えていて。その時、山崎さんが作っていた号は、ほとんどできあがっていたにも関わらず、いきなりすごいスピードで記事を入れ込んでくれて。それくらいの何かを感じていただいたからだと思うのですが、本当にびっくりするくらいのスピードでいろんなことが決まりました。あの時はほとんど味方がいない状態だったので本当に有り難かった。とにかく味方を作ることが僕のテーマでした。
山崎 最初に鬼束さんの歌を聴いた時、とてつもない才能だと直感したのを鮮明に憶えています。
土屋 それをそのまま分かってもらえたことが、何より嬉しかったんです。
山崎 鬼束さんへの最初のインタヴューは六本木のオフィスで、ただならぬマグマを感じました。静かで全然喋らない。歌詞のことを訊くと、「全然考えてない、降りてきてる」と答えて。
土屋 雑誌の取材も大変だよね(笑)。彼女が言っていたんだけど、とにかく生きていて絶望して、「何で生まれてきたんだろう?」というサイクルに陥って「もう駄目だ」と思った瞬間に言葉が降りてくるんだそうです。その言葉で正気に返るって。デビュー前ですよ。そんなことを言う17〜8歳の少女が目の前にいたら「何としても世に紹介しなきゃ!」となるわけですよ。
山崎 ドラマ『トリック』のタイアップがついたとはいえ、「月光」はものすごい速さで、そして爆発的に売れました。代表曲になりましたが、特別な曲だという感覚はありました?
土屋 ありました。デモ・テープの時点で。彼女の雰囲気含め、持っているものが「月光」は世の中にストレートに伝わるんじゃないか?と思いました。なので、当初はアルバムの前にリリースさせようと考えていたんです。本当に小さなデビューだったので、1stアルバムまでに一番シンプルに、ミニマルに彼女が伝わりやすい楽曲をリード・シングルに置こうと思っていて。まさか2枚目でこんな展開がくるとは想像もしていなかったので、突如攻守が入れ変わったというか(笑)。いきなりドラマの主題歌に抜擢されたこともそうですが、本当にいろんな偶然が折り重なった感じがあって。急に夢のように売れたけれど、そのおかげで、こちらのプランは相当な変更を余儀なくされるじゃないですか? 僕は、プロデューシングの時のキャリア・マネジメントとして 本人が辞めることを望むなら別だけど、そうでないなら 1日でも、1時間でもいいから長く時代に留まり、目の前のものと向き合って表現活動をして欲しいんです。そのためのプロデューシングだと思っていて。もちろん、売れないより売れた方がいいですよ。だけど、売れる以前に、どうやったらこの才能が長くこの時代に滞留できるか?を考えた時に、あまりにも予想外なことが起こり過ぎていました。1枚目はインディーズみたいな規模だったのに、2枚目はテレビで歌いまくっているみたいな、そういう状態になっちゃったわけで。そうなると、どうやってこの騒ぎを鎮火させればいいか?を考えるようになって。この前までゲリラ戦法だったのに、急に一発屋防止みたいなマインドに半年も経たないうちにどんどん変わり。そればかり考えていましたね。それで、本来2枚目に出そうとしていた「Cage」を3枚目のシングルにシフトさせ、「月光」が毎日売れている最中に出す決断をしました。やっぱり本社は大反対して、当時の社長としょっちゅう押し問答になり。「まだ売れているのに何で次を出すんだよ!」と。僕は、「違います。逆に売れているから出すんです。この曲で終わってしまったら困ります。とにかくみんなの意識を『月光』から逸らしたい」と言って喧嘩になりました(笑)
山崎 苦労して苦労してやっと売れたという渦中に、その判断ができる人、いないですよ。
土屋 僕の中で一番重要なことがあったんです。デビュー前、スタッフにも言ったのですが、音楽にはいろんな種類があるんですよね。カラオケでみんなで歌うと盛り上がる曲がある一方、鬼束の曲は愛されたとしても必ず1対1だろう。歌とリスナーが1対1になる図式をどれくらい作れるかが大事なんだと。この歌を好きになってくれるリスナーは、必ず曲と自分が1対1になっていると捉える確信があったので、尚更「月光」のヒットやロング・セールスが怖くて。「みんなの鬼束ちひろ」にはなってはいけない、「僕の」「私の」鬼束ちひろで留めておかないと絶対にダメだということをずっと思っていました。
山崎 そういった意味でも、ターニング・ポイントだと思っているのは、2001年9月7日にリリースした5枚目のシングル「infection」です。
土屋 「infection」もデビュー前から既にあったんです。本当にすごい子ですよ。1stアルバムの『インソムニア』が爆発的に売れた後、全く迷いなく「次は『infection』しかない」と。人生でああいう曲(フル・オーケストラ編成のクラシック楽曲)を、しかもシングルで出せる機会は普通はないですね。メジャー・レコード会社で売り上げを見なきゃいけない立場にいたら、間違いなくできないですよ。でも当時は1stアルバムの成功で世間の注目が集まっていたので、「ここで出せ」という神様の思し召しなのだと感じたのを未だに覚えています。
山崎 それまで僕は『バァフアウト!』で取材、そして連載で関わってきましたが、ここからクリエイティヴ・ディレクションとして、スタッフに呼んでもらいました。
土屋 山崎さんの存在は大きかったです。鬼束は、相手が何かの意図を持っているのを見抜くのが上手だから、オーガニックに付き合える人がすごく少ないんです。そうするとマスコミのみなさんもですが、マネージメントやレーベルのスタッフで意図を持って仕事をしていない人はまずいないから、本人にとってはどこか不純なんですよね。100万枚以上売れていて、オーガニックというのも難しい話ですが。でも関係なく、純粋に自分と向き合ってくれる人を見抜くんです。山崎さんは間違いなくそのうちの1人でしたね。
山崎 曲にインスパイアされ、顔が写っていないジャケットにしてしまって。
土屋 インパクトがありましたよ。いろんな意味であの作品は、自分のキャリア全部を通しても、強烈な思い出になっています。彼女とのキャリアの中での自分のピーク・アチーヴメントだった気がします。
山崎 今回アナログにもなって嬉しかったのが3rdアルバム『Sugar High』です。名盤中の名盤。リマスタリングされた1枚を聴き、改めて感動しました。
土屋 原点回帰のアルバムでした。いろんなことがあった後でしたが、とても良いクオリティで作れました。1つのアルバムの完成度、佇まいなど全部考えられた、すごくよくできている作品です。自分も、仕事のテリトリーで1人の人間とここまで向き合ったことはないわけで、そうすると、当然ですが、自分にも反省や成長があったりします。作ってる時は一緒に仕事をする最後のアルバムになるとはもちろん思わなかったけど、結果的にはこれが最後になりました。
山崎 シングル曲は1つも入っていないんですよね。その意図は何だったのでしょうか?
土屋 実は2ndアルバム(『This Armor』)やそのプロモーションで、ちょっと欲張って幅を広げ過ぎたかなと思っていた時期だったんです。もちろんこれも「月光」だけじゃないぞキャンペーンの一環としてですが。いろんなものを短時間でこなしてきたけど、実際は『インソムニア』が成功して、いろいろ大きな変化が起きていて。恐らく本人にはいろんなものがのしかかっていて、デビュー前とは違う「生きにくさ」を毎日のように感じていたと思います。僕としても、この状態に対して原点回帰するために 彼女がシングルやテレビ出演など、メディア露出を含めた宣伝活動自体に懐疑的になっている様子も感じられて 宣伝やシングルとは関係ない、今の自分を切り取ってアルバムを出そう、と。とはいえ2ndアルバム『This Armor』を出したばかりだったので、音楽プロデューサーとしてはタイミングは近過ぎたけど、マネージメントの責任者として、今のこの子のメンタリティをリセットしたいというか、元に戻したい、落ち着かせたいという想いが強くて。「お前はここにいるんだぞ」ということを、1回感じ取ってほしくて、シングルを考えずに、急いで作ったわけじゃないですが、制作を始めました。そうしたらたまたま〈日本武道館〉が取れて。発売前に〈武道館〉で新曲を全部発表しようみたいな。それも変わっているんだけど、誰も知らない曲を〈武道館〉でたくさん披露するっていうチャレンジを 世の中に適応しない人の呼吸感というか、時にエキセントリックになったとしても 表現できるんじゃないか?という気持ちがありました。後から意図的にという部分もあるんだけど、1枚目から3枚目は全部が密接に関係していますね。
山崎 アルバムを聴いて感じた圧倒的な作品性をアートワークで表現したら、特殊パッケージ仕様が本社から怒られたんですよね。
土屋 でも、山崎さんじゃなかったら、絶対にこのジャケットにはならなかったですから。1曲聴いたら、「このジャケットと曲のギャップは何だろう?」とか思うじゃない? でも、この子の中に確実にある、生きづらさからエキセントリックになっちゃうメンタリティがあったと思うんです。そして、このジャケットはそこを切り取っているなと思いますよ。何から何まで破天荒な3枚目ですよね。ヴィジュアルも、在り方も発表の仕方も。もう1回同じことをやれと言われても、できないです。
山崎 それにしても、ボックス・セットに収録されているTV番組『神が舞い降りる瞬間~鬼束ちひろ・22歳の素顔~』の映像にも映し出されている、〈武道館〉の楽器編成はかなり特殊でしたよね。
土屋 ピアノ2本から始まって、オーケストラ、そして最後にバンドが出てくるという3部構成になっていたんだよね。その〈武道館〉も、本人が立ちたいと言ったんだよね。何だか分かんないけど、彼女の場合、理由はないんだよね。そこで歌いたいみたいなことがあるだけ。でも象徴的な感じだったな。
山崎 最初はパフォーマンスに対して、そんなに積極的ではなかったと?
土屋 消極的というわけではないけれど、ステージに立ったこともほぼなくて。やり方がわからない、でも自分はこの人生を選んだ。私はここで戦うしかない、歌うしかないという、腹が据わる感じだったと思います。瞳孔も開きそうで。僕、彼女の歌っている顔がすごく良いなと思っていました。歌っていない時は「辛い」とか何とか言っていても、歌う時には生気をものすごく感じて。メロディや歌詞とは別の次元でね、リアルに伝わっていくものを持っている。理屈じゃないんだけど、歌っているときの表情というか、顔が、とても魅力がある。これで歌われたら、本当に曲が突き刺さってくるんじゃないかとさえ思いますよ。
山崎 パフォーマーとして〈武道館〉という大きな空間を完璧に支配していましたね。
土屋 そこにしか居場所がない者の必死さが生み出すものなんじゃないか?と思いますね。作って歌う以外のことに興味がないわけだから。選曲とか、自分が歌う歌がどうだとか何も興味ない。ミックスの出来上がりも聴かない。とにかく作って歌う、あとは任せる。レコーディングの歌もそうだけど、特にライヴ、お客さんを前にして歌うことに関しては、本人は戦いだと言っていました。
山崎 2003年リリースの『Sign』、『Beautiful Fighter』、『いい日旅立ち・西へ』、『私とワルツを』の4枚のシングルのアートワークとミュージック・ヴィデオは、『Sugar High』から一転して、徹底的に綺麗に美しく撮りました。
土屋 すごく良かったです。
山崎 振り幅として、1人のアーティストの中に、美しさと狂気の両方が共存していることを表現しようと。
土屋 雑誌を作っている人にサポートしてもらうって前代未聞だよね。気が付いたらマネージャー業に近いことまでしてくれていて。そんなことあり得ないよね。今この記事を読んでいる人も何のことか分からないと思うよ(笑)。
山崎 スタイリストとヘアメイクさんと共にツアーにも帯同して。『ミュージックステーション』の特番で、「鬼束ちひろSTAFF」と書かれた入館パスを下げてたら、他のレコード会社の方から「山崎さん、ここで何してるんですか?」と驚かれたり(笑)。
土屋 (笑)それにしても、本当にいろんなことを思い出してきた。『UN AMNESIAC GIRL ~First Code (2000 – 2003)~』のリリースを機に、3枚のアルバムとこんなにも正面から、20年振りに向き合うことになるとは思わなかったです。しかも3枚まとめて。みなさんの力を借りながら、一生懸命歌ってきた鬼束はやっぱりすごい。流行に関係なく、新しいわけでも古いわけでもない、非常に普遍性のあるものとして音楽を産み出し続けてきた。純粋なリスナーにやっとなれた気がします。「鬼束ちひろの曲、良いな」と思えるリスナーになるには、この月日が必要だったのかもしれない。すごく良い曲たちだと思います。僕自身も、鬼束と出会って成長できました。1回1回、1日1日の局面はもう必死過ぎてよく覚えていないけれど、振り返ってみたら、ひとりの「個」のアーティストととことん向き合うということは、こういうエンターテインメントの究極的な仕事なんだなと思います。

『UN AMNESIAC GIRL ~First Code(2000 – 2003)~』鬼束ちひろ
発売中
〈ユニバーサルミュージック〉

『インソムニア』
発売中
〈ユニバーサルミュージック〉

『This Armor』
発売中
〈ユニバーサルミュージック〉
『Sugar High』
発売中
〈ユニバーサルミュージック〉
INFORMATION OF CHIHIRO ONITSUKA
【WEB SITE】
www.onitsuka-chihiro.jp
【facebook】
www.facebook.com/onitsukachihiro.official
【X】
@onitsukachihiro
【YouTube】
www.youtube.com/channel/UCugqe_jjVjIOVgDdtBLAVjA